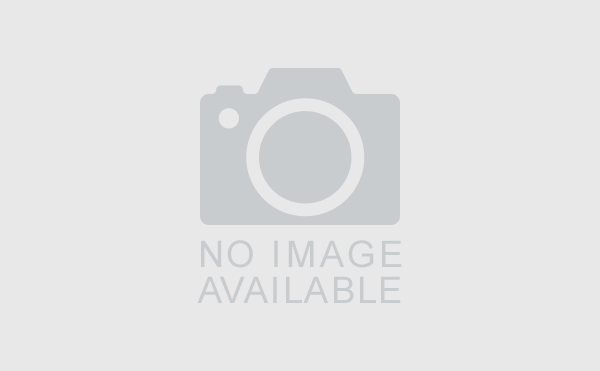有機農家は平行線を穿つ。なぜなら自由であるために。

田畑というと正方形や長方形、せめて台形が普通ですが
中山間地のあさひや農場の圃場はそういう四角四面な田畑はほとんどなく
極めてフリーな感じのエクストリーム不定形な形をした畑が多く存在します。
そんな畑でも端から一面にレタスとか白菜をずーっと植えていく単純画一な畑ならそれほど問題ありませんが、
「畑のある部分に白菜を植えてその46m横にキュウリがあってその中間に2m幅でエダマメを植える。」
そんな極めてフリーな感じのエクストリーム少量多品目な有機農業をやっていると
気がつくとへんなところ隙間ができたりしてかなり不便です。
畑の長さや広さがわからないと苗の数やら肥料の量が無駄になったり足りなかったりと困ることになります。
そういうわけであさひや農場では新しい畑はまずきちんと測量を行います。
が、測量を行って何年もたつと当時つけた目印の杭が草刈機で切られたりトラクターで踏まれたり狸に持っていかれたりとそれはもう酷い目にあって消えていくので、
今年は改めて測量しなおすことにしました。
単純に面積だけなら今はグーグルマップから簡単に計算できるので良いですが、
あさひや農場の不定形な畑では、畑の中に基準となる平行線を何本も引き基準点を実際に畑に打っていく必要があります。
そうでないと実際に畑に肥料を巻くときや耕すときに耕す方向を間違えたり曲がったりするからです。
 凍てついた大地にハンマーで鉄棒を打ち込み基準を作り、線を引き、紐で三角形を作って直角を出す。
凍てついた大地にハンマーで鉄棒を打ち込み基準を作り、線を引き、紐で三角形を作って直角を出す。
直角を出すことで平行線を作っていく。不定形な畑を二辺が平行な台形で短冊状に区切っていきます。
下の図のような感じになります。単に面積を出すだけなら下記のようなマップでいいのですが、
実際に畑で絵のように分けれるように杭を打つ作業が必要なのです。

畑を10m幅に区切りました。
数字の単位はmもしくは平方メートルです。
9枚に分かれました。
実際に使うときはこの1区画に2~3品目くらいの作目が入ることもあります。
葉物などは2回か3回は収穫するのでこの畑1枚で1年に30品目以上は作ります。
普通の農業ではこんなに細かく分かれません。
私がここを使う前の農家はこの畑一枚でレタスだけを作っていました。
レタスをどばーっ!と一度に植えて、どばーっ!と数日で出荷します。
ちょっと考えると、冒頭で書いた
「極めてフリーな感じのエクストリーム少量多品目な有機農業」というのもあながち大げさでないなと。
我ながら身震いするのです。
というか風邪かも。。。