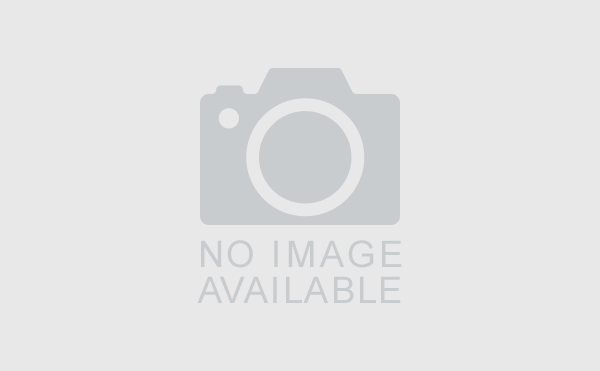「こいつらを全員馬鹿と思え」集団土壌分析のコツ
例年やってる土壌分析を地元の仲間で集まってやりました。
土壌分析はセッティングに非常に時間がかかるため
(毎年土壌分析のキットを開いて「う~ん これどうやるんだっけ?」からスタート)
10件の有機農家ががこれを各個にやると全体で10回のセッテイングで悩まねばならず、
これをまとめて1回で済ますだけでも随分頭の良いことです。
それでも普段は各農場別々の「社長様」が集まるわけですから、
(おそらく普段は優秀な秘書がやってくれるのでしょう)なかなか足並みも揃わず、
普段なら「ちゃんとよく見て!」とか「注意して!」とかスタッフに言ってるようなミスが多発します。
それでも本来なら、「人は褒めて育てる」べきなのでしょうが、
土壌分析会は時間もなく失敗も許されないので、
お互いに「こいつらは全員馬鹿と思え!」というくらいに思って、お互いを注意散漫な幼稚園児で絶対失敗することを前提とします。
まずは全体の仕事の流れを考えて作業工程を配置。
各工程では「マシーン」となってひたすら試験管洗い、ひたすら容器組み立て、ひたすらph測定、ひたすら検査液スポイト、と分かれます。
室温は土壌分析用に20度以上なので2月の佐久穂の室内と思えないくらい薄着です。
例えば「土壌から肥料分を抽出する」容器の組み立て。
何度言ってもみんな馬鹿なので単純な容器の組み立てもろくにできません。
組み立てるときは一つ一つ組み立てるのではなく、
10個なら10個、蓋をして並べて「全部揃ってるか確認」し、
スポンジを挟んでは並べて「全部揃ってるか確認」し、
全部出来たら「全部揃ってるか確認」しを繰り返してもらいます。
そうすると1個づつ組み立てるより間違いも減り、何より本来すべき確認が10分の1になるので、
おしゃべりに集中できます!
試薬反応工程では各土壌から抽出したアンモニア態窒素、硝酸態窒素、リン酸、カリウム、カルシュウム、マグネシュウム、鉄、マンガン用の8つの試験管のうち
4つの試験管に水を加え
全部で15の試薬を加えます。試薬の中には「試薬Aを入れてから3分後にBを入れる」や「試薬投入後10分待つ」などあるので入れる順番なども複雑です。
写真では7個分の土壌を調べていますので試験管数は56本。
私達のグループでは最大で同時に11個の土壌を同時に試験できますので試験管が88本並ぶ時があります。
こういう時に意外と時間がかかるのが「え~っと次の反応試薬は~」と次の作業にかかるセットアップの時間ですので、
こうやって一つの工程を一気に多数出来るだけでも時間が短縮できますし、ミスも減らせます。
写真では3人のマシーンがひたすら割り振られた試薬を試験管に投入していっています。
割り振っても各マシーンには3~6個の試薬が割り振られるので、
ちゃんと紙に試薬の瓶を戻す場所を描いて用意して「使った瓶はちゃんとここに戻しましょうね^^」と優しく教えてあげます。
ここで注意しないといけないのは、「スポイトのメモリを読むときは目盛と目線を同じ高さにしろ!」という基本動作の欠如です。
こればかりは慣れていないと何度言ってもすぐいい加減になるので、「絶対こいつらミスするぞ!」と監視しまくります。
いい加減な姿勢でやろうものなら後ろから蹴り倒して襟首を掴んで引きずり出し、窓から凍てつく雪原に放り出します。
写真で見ればわかるように何度も放り出されてる人ほど厚着で、慣れるほど自信を持って薄着で作業に挑みます。
分析の最終工程がデジタル分析器による成分値の読み取りと記録・確認です。
本来は太陽光のもと目視で反応液の色や濁り具合を視て数値を出していました。
山に沈みゆく夕日を軽トラで追いながらマグネシュウムのオレンジ色から数値を読むという正確さもへったくれもない
ピテカントロプス・エレクトス的な土壌分析石器時代を過ごしてきたあさひや農場としては
昼間の室内でも正確に数値が読み取れるデジタル検定機はまさに鋼の剣です。
ここには熟練者が配置され、デジタル検定機から出た数値から異常値をはじき出しだします。
「この数値おかしい、試験するときB液入れた?」「土壌から抽出した液は濁ってない?」
こんな感じで異常値を割り出して、そこはすぐに再試。
更に全ての数値をPCに入れてこれまでの数年間の数値と照らして異常を検知します。
特にCECという値は早々毎年変わるものではないので、検出値からCECを出して確認します。
このように「ミスがあるもの」を前提で土壌分析を進めます。
馬鹿が一人だと馬鹿で終わりですが、馬鹿が大勢集まるとなんとかなります。
バカ同士お互いを疑い合うってなんて素晴らしいのでしょう。
去年撒いた肥料は十分作物に吸われたか?残っているとしたら何が原因か?
毎年のデーターとも照らしあわせて、畑がどんな方向に向かっているのか過去を振り返り、
そしてこれから畑をどのようにしていくのか、未来を設計していきます。